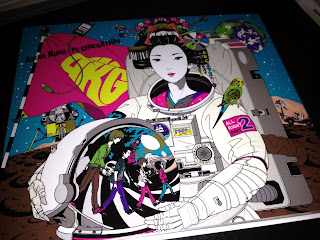It's A Musical
http://www.itsamusical.com/
Point Back/It's A Musical
クリスマス前に青山のCIBONEで買い物をしていた時、流れていたBGMが気になったのでiPhoneに聴き取らせてみたら、It's A MusicalのPoint Backという曲であった。
主張しない、ごく控えめな曲であると思う。
少しレトロな電子音のようなオルガンと、軽快なリズム、耳ざわりの良いボーカル、シンプルな構成。でも、何かひっかかるものを感じる。
こういったごく近い距離感を持つ音楽は、寒い季節に暖かい布団のなかで丸まっているときのような、極めてプライベートなシチュエーションで聴きたくなるものである。
もう一曲。
One Million People/It's A Musical
バンドはスウェーデン出身のElla Blixtと、ドイツ出身のRobert Kretzschmarの二人組。
Wikipediaの記事は、ドイツ語のものしか見つけられなかった。⇒Wikipedia
日本のアーティストとも交流があるようで、バンドのプロフィールは下記のホームページに詳しい。
http://www.rallye-label.com/?pid=38235412(RALLYE LABEL)
2012/12/29
2012/12/18
Live@Studio Coast/Two Door Cinema Club
新木場のStudio Coastにて行われた、Two Door Cinema Clubのライブを観に行ってきた。
新木場駅から会場までの道のりには、予想外に多くの人が歩いていた。今回の東京公演はソールドアウトであったという。
会場のロッカーはなんと屋外も屋内も全て埋まっており、コートを手に持って観ることになってしまった。それほど多くの人が集まっていたということか。
サポートアクトのCitizens!終盤から会場に入り、少し高い位置から眺めるような形で陣取り。客層は男女ともに同じくらいの割合で、意外と若い(大学生くらいの若者多し)。
ライブの開始を待つソワソワとした高揚感、嵐の前の静けさのようなザワつき、バンドが登場したときの歓声、会場の一体感。久しぶりのライブであったが、やはり生で観るのはいいなあと、しみじみ思う。
時間にして1時間強。トークに割いた時間もほとんどなく、初めから最後まで一気に駆け抜けるようなライブであった。あっという間に終わってしまい、”あっさりしているなあ”などと思っていたが、あらためて振り返ると、意外と曲数が多いことに驚く。
彼らが発表している曲ーアルバム2枚分に日本盤ボーナストラックの2曲を加えた23曲のうち、18曲も演奏している。ライブで演奏されなかった5曲は、1stのうち#1:Cigarettes In The Theatre、2ndのうち#8:Settle、#9:Spring、#11:Beacon、それに1st日本盤のボーナストラック:Kidsである。個人的にはCigarettes In The Theatreが聴けなかったのは残念であった。
演奏は、Youtubeで観られるライブ映像やライブ音源を収録したアルバムで聴いていたとおり。演奏のリズムが崩れることなどもなく、完成度は高い(無難すぎるとも言えるが、それはバンドの若さ故であろう)。
ステージも装飾の一切ないシンプルなものであったが、目まぐるしく動きまわるライトの演出は印象に残っている。
比較的ストイックなライブであったが、曲が終わるごとにフロアーは拍手に包まれており、初めから最後までずっと盛り上がっていた。
ボーカルのAlexは、途中キーボードにもたれかかるなど息切れしている様子であったが、歌声には全く疲れを見せず、終始安定していた。
ギターのSamは、いつもどおりの演奏スタイル(小刻みに身体を捩るギターの弾き方)で、ライブ中はよく動き回っていた。ベースのKevinは、シャツの袖をいつもどおり高い位置まで捲り上げ、直立不動で演奏する姿が印象的であった。
曲単位で盛り上がったのは、まず2曲目のUndercover Martyn。声を出して歌っている人の、なんと多いこと(サビの前、To the basement people, to the basement…の部分!)。そしてやはりI Can Talk、Somedayといった激しめの2曲も人気がある。
個人的には、ライブの中盤で聴くNext Yearが新鮮であった。
今まであまり意識していなかったが、どの曲も間奏部分のテンポが良く、どの曲も踊れる。Two Door Cinema Clubは、何ともライブ映えのするバンドであった。
アンコールの3曲目である最後の曲に、このバンドを知るきっかけとなった”What You Know”が演奏されたため、思いがけず感慨に耽ってしまった。
会場の雰囲気も良く、気持ちの良いライブであった。
セットリストは以下のとおり。
1.Sleep Alone
2.Undercover Martyn
3.Do You Want It All?
4.This Is The Life
5.Wake Up
6.You're Not Stubborn
7.Sun
8.Pyramid
9.I Can Talk
10.Costume Party
11.The World Is Watching
12.Next Year
13.Something Good Can Work
14.Handshake
15.Eat That Up, It's Good For You
16.Someday
17.Come Back Home
18.What You Know
2012/12/02
相互理解の難しさ/Lost In Translation
Lost In Translation/Sophia Coppola
ウイスキーのCM撮影のために来日したハリウッド俳優:ボブ・ハリスと、カメラマンである夫の仕事に同行し来日、東京に滞在する新妻:シャーロットが、東京のホテルで出会う。
共に孤独や疎外感を感じていた二人は、自然と距離を縮めていき、束の間の理解者として触れ合い、東京での時間を共有する。
端的にいうならば、相互理解の難しさを、異国の地で周囲に馴染めず孤立する二人の目線によって描いた作品である。
映画の題材は、単に”異国の地で感じる孤立感や虚無感”といった限定的なものではなく、より普遍的な、”ふとした時に誰しもが感じうる孤独感や疎外感、周囲の人間や状況との間に隔たりを感じ、自分を見失いそうになる時の不安”といったものであると感じた。
タイトルも、直訳すれば、言語の違いによって生じる齟齬により、本来の意図が失われるということであろうが、この映画はそれよりもずっと広い意味で、相互理解の過程で失われる様々なものを扱っている。
レンタルショップでは”ラブストーリー”の棚に置かれていたが、この作品を、”慣れない異国の地で孤独な男女が出会うラブストーリー”とみるのは、表面的であると思う(実際、二人が男女の関係になることは、最後までない)。
ソフィア・コッポラ自身が日本に滞在していたことがあるそうで、その際の体験が話の元になっているようだ。
滑稽に見える程にステレオタイプを強調された日本の姿に、首を捻りたくこともある(レビューを読んでいても、その点に不快感を感じたとの意見は多い)が、舞台が日本であるという点や、日本に馴染めない米国人といった題材に、殊更に注目する必要はないだろう。
異国に滞在し、風俗、文化、国民性などの違いからその土地に馴染めないという状況は、題材となる”意思疎通の困難さ”を際立たせるためのシチュエーションとして選ばれているに過ぎない。
普段の生活において、仕事やプライベート等、忙しく動き回っている時には迷いや不安なんて感じている暇はないが、ふと1人で自由に使える時間ができたりすると、何をしてよいのか意外に分からなかったりする。そういった時に、孤独感や不安を感じることはあるが、救いとなるのは、時間を共有できる何気ない誰かの存在であったりする。
そういった”誰か”の大切さを、強く実感させられる映画であった。
他の”日本を舞台とした映画”にはない独特さもさることながら、題材の持つ普遍性の高さに共感を得られているからこそ、この映画は高い評価を獲得することが出来たのだと思う。
先に帰国することになるボブがホテルを離れる際、後ろ髪を引かれるようにしてシャーロットのことを気にかける姿は何ともやり切れない。
リムジンに乗り込み空港へと向かう路の途中、人ごみの中にシャーロットの後ろ姿を見つけ、別れの挨拶をしに行くシーンは、さっぱりとしていながらも余韻があり、とても良い。
二人が別れるシーンで流れる、Jesus And Mary ChainのJust Like Honeyは印象的である。
Phoenixの音楽も使われており(この映画を手に取ったきっかけの一つである)、作中でToo Youngを聴くことができる。
ウイスキーのCM撮影のために来日したハリウッド俳優:ボブ・ハリスと、カメラマンである夫の仕事に同行し来日、東京に滞在する新妻:シャーロットが、東京のホテルで出会う。
共に孤独や疎外感を感じていた二人は、自然と距離を縮めていき、束の間の理解者として触れ合い、東京での時間を共有する。
端的にいうならば、相互理解の難しさを、異国の地で周囲に馴染めず孤立する二人の目線によって描いた作品である。
映画の題材は、単に”異国の地で感じる孤立感や虚無感”といった限定的なものではなく、より普遍的な、”ふとした時に誰しもが感じうる孤独感や疎外感、周囲の人間や状況との間に隔たりを感じ、自分を見失いそうになる時の不安”といったものであると感じた。
タイトルも、直訳すれば、言語の違いによって生じる齟齬により、本来の意図が失われるということであろうが、この映画はそれよりもずっと広い意味で、相互理解の過程で失われる様々なものを扱っている。
レンタルショップでは”ラブストーリー”の棚に置かれていたが、この作品を、”慣れない異国の地で孤独な男女が出会うラブストーリー”とみるのは、表面的であると思う(実際、二人が男女の関係になることは、最後までない)。
ソフィア・コッポラ自身が日本に滞在していたことがあるそうで、その際の体験が話の元になっているようだ。
滑稽に見える程にステレオタイプを強調された日本の姿に、首を捻りたくこともある(レビューを読んでいても、その点に不快感を感じたとの意見は多い)が、舞台が日本であるという点や、日本に馴染めない米国人といった題材に、殊更に注目する必要はないだろう。
異国に滞在し、風俗、文化、国民性などの違いからその土地に馴染めないという状況は、題材となる”意思疎通の困難さ”を際立たせるためのシチュエーションとして選ばれているに過ぎない。
普段の生活において、仕事やプライベート等、忙しく動き回っている時には迷いや不安なんて感じている暇はないが、ふと1人で自由に使える時間ができたりすると、何をしてよいのか意外に分からなかったりする。そういった時に、孤独感や不安を感じることはあるが、救いとなるのは、時間を共有できる何気ない誰かの存在であったりする。
そういった”誰か”の大切さを、強く実感させられる映画であった。
他の”日本を舞台とした映画”にはない独特さもさることながら、題材の持つ普遍性の高さに共感を得られているからこそ、この映画は高い評価を獲得することが出来たのだと思う。
先に帰国することになるボブがホテルを離れる際、後ろ髪を引かれるようにしてシャーロットのことを気にかける姿は何ともやり切れない。
リムジンに乗り込み空港へと向かう路の途中、人ごみの中にシャーロットの後ろ姿を見つけ、別れの挨拶をしに行くシーンは、さっぱりとしていながらも余韻があり、とても良い。
二人が別れるシーンで流れる、Jesus And Mary ChainのJust Like Honeyは印象的である。
Phoenixの音楽も使われており(この映画を手に取ったきっかけの一つである)、作中でToo Youngを聴くことができる。
2012/11/23
音楽のキャパシティについて/Death Cab For Cutie
いわゆるAlternative Rockという括りは、Wikipediaの記事を読めばわかるとおり非常に曖昧なものであるが、自分にとってのAlternative Rockとの出会いは、米国はシアトルのバンド、Death Cab For Cutieであった(このページにバンドの名前が載っているので、彼らをAlternative Rockに属するバンドと考えていいだろう)。
Death Cab For Cutieは、今では最も好きなバンドの一つであり、2009年に来日した際には新木場のStudio Coastにも足を運んだ。
しかし、初めて彼らの音楽を聴いた当時の印象は、”退屈な音楽”であった。
最初に手に取ったのは5thアルバム:Plans(2005年)であり、新宿のタワーレコードで試聴したそのアルバムを、購入しようかどうか一頻り迷ったあげく、Alternative Rockの世界へと足を踏み入れる決意をしたのである。
背中を押したのは、#2:Soul Meets Bodyであった。
Alternative Rockの世界に…云々と言っておいて何だが、こういうキャッチーな曲が一つもなかったら、当時の自分がアルバムを手にとることはなかったかもしれない。
本作より、アルバムのリリース元がBarsuk Records(ジャケットに描かれた犬のアイコンが印象に残っている)からAtlantic Recordsへと変わっているが、各曲に漂う澄んだ空気感や、前作までとは毛色の違う統制された雰囲気は、やはりメジャーデビューの為せる技であろうか(アルバムのプロデュースは、前作と同じくバンドのギタリスト:Chris Wallaである)。
同じ傾向は次作である6th:Narrow Stairsにも引き継がれるが、個人的にはこの2作がとても好きである。
昨年リリースされた7th:Codes & Keys(2011年)はまた違った傾向の作品であるが、個人的な評価はそれ程高くはない。
Plansと並行して、彼らの2nd:We Have The Facts And We're Voting Yes(2000年)、3rd:The Photo Album(2001年)も聴いていたが、その独特の暗さ(表現のしようはいくらでもあるだろうが、当時の自分にとっては、ひたすら陰鬱な音楽という印象であった)に、聴くたびに憂鬱な気分になっていたものである。
しかしまあ、これが所謂オルタナというやつなんだろう…などと考えており、懲りもせずに何度も聴き続けた結果、ここに1人のDeath Cab For Cutieファンが生まれることとなった。
ちなみに2nd、3rdに続く作品としてリリースされた4thアルバム:Transatranticism(2003年)で、バンドは信じられないくらいの変化を遂げている。
各曲に存在感があり、また多様性にも富んでおり、キャッチーでありながらもバンドらしさが失われておらず、非常に完成度の高いアルバムである。
音楽に対するキャパシティというのは面白いもので、多種多様な音楽を聴いていくなかで、知らず知らずのうちに広がっていくものである。
繰り返し聴き続けることで、自分の嗜好が明らかに変化をしていることが分かる。これまで耳に馴染まなかったバンドの曲も、目の覚めるような名曲に聴こえる。
そうやって、少しずつお気に入りは増えてきた。
音楽との付き合い方は人それぞれであるけれども、ある種、荒療治のようなかたちで無理して新しいジャンルの音楽を聴き続けることだって、キャパシティを広げるために、時には必要なことなのだと思う。
http://www.deathcabforcutie.com/
Death Cab For Cutieは、今では最も好きなバンドの一つであり、2009年に来日した際には新木場のStudio Coastにも足を運んだ。
しかし、初めて彼らの音楽を聴いた当時の印象は、”退屈な音楽”であった。
最初に手に取ったのは5thアルバム:Plans(2005年)であり、新宿のタワーレコードで試聴したそのアルバムを、購入しようかどうか一頻り迷ったあげく、Alternative Rockの世界へと足を踏み入れる決意をしたのである。
Alternative Rockの世界に…云々と言っておいて何だが、こういうキャッチーな曲が一つもなかったら、当時の自分がアルバムを手にとることはなかったかもしれない。
本作より、アルバムのリリース元がBarsuk Records(ジャケットに描かれた犬のアイコンが印象に残っている)からAtlantic Recordsへと変わっているが、各曲に漂う澄んだ空気感や、前作までとは毛色の違う統制された雰囲気は、やはりメジャーデビューの為せる技であろうか(アルバムのプロデュースは、前作と同じくバンドのギタリスト:Chris Wallaである)。
同じ傾向は次作である6th:Narrow Stairsにも引き継がれるが、個人的にはこの2作がとても好きである。
昨年リリースされた7th:Codes & Keys(2011年)はまた違った傾向の作品であるが、個人的な評価はそれ程高くはない。
Plansと並行して、彼らの2nd:We Have The Facts And We're Voting Yes(2000年)、3rd:The Photo Album(2001年)も聴いていたが、その独特の暗さ(表現のしようはいくらでもあるだろうが、当時の自分にとっては、ひたすら陰鬱な音楽という印象であった)に、聴くたびに憂鬱な気分になっていたものである。
しかしまあ、これが所謂オルタナというやつなんだろう…などと考えており、懲りもせずに何度も聴き続けた結果、ここに1人のDeath Cab For Cutieファンが生まれることとなった。
ちなみに2nd、3rdに続く作品としてリリースされた4thアルバム:Transatranticism(2003年)で、バンドは信じられないくらいの変化を遂げている。
各曲に存在感があり、また多様性にも富んでおり、キャッチーでありながらもバンドらしさが失われておらず、非常に完成度の高いアルバムである。
音楽に対するキャパシティというのは面白いもので、多種多様な音楽を聴いていくなかで、知らず知らずのうちに広がっていくものである。
繰り返し聴き続けることで、自分の嗜好が明らかに変化をしていることが分かる。これまで耳に馴染まなかったバンドの曲も、目の覚めるような名曲に聴こえる。
そうやって、少しずつお気に入りは増えてきた。
音楽との付き合い方は人それぞれであるけれども、ある種、荒療治のようなかたちで無理して新しいジャンルの音楽を聴き続けることだって、キャパシティを広げるために、時には必要なことなのだと思う。
http://www.deathcabforcutie.com/
2012/11/18
個人的に思い入れの強いバンド/Keane
ボーカル&キーボード&ドラムの3人組による、ギターレスの3ピースバンドという特異な組み合わせでデビューしたKeane。
2012年には通算5枚目のアルバムであるStrangelandをリリースし、先日、渋谷AXにて行われたライブもなかなかの盛況であったとのことである。
個人的には、初めて購入した洋楽のCDが彼らの1stアルバム:Hopes And Fearsであったこともあり、バンドに対する思い入れは強い。
出会いは、たまたま聴いていたラジオで流れたEverybody's Changingの一節「So little time, try to understand that I'm」を聴いたことであった(Glastonbury festivalsの特集にて、ニューカマーの一人として紹介されていたのだ)。
聴いた瞬間に"体中に鮮烈な衝撃が走った"…とかそういった類の特別な経験ではなかったが、まだ高校生で、背伸びをして努めて洋楽を聴こうとしていた当時の自分に、そのメロディが何かを感じ取らせたことはよく覚えている。
直後に発売したデビューアルバムを、あまり潤沢とは言えない小遣いから捻出したお金で購入した。
彼らのアルバムの中からベストを選べと言われたら、自分は間違いなく2ndアルバム:Under the Iron Sea(邦題:アンダー・ザ・アイアンシー〜深海〜)を挙げる。
Keaneは、デビュー当初から美メロやピアノロックといった言葉で形容され、曲の持つ美しさによって注目を集めていた。
実際、メロディは美しく、1stアルバムは全曲"聴ける"アルバムであった(凡庸なアルバムには必ず1、2曲は退屈な曲が混じっているものだが)。
1stアルバムの成功後、バンドは自らのイメージに悩み、世の中の多くのバンドがそうするように、2ndアルバムを作ることによって1stからの脱却を図ろうとした。
2ndアルバムでまず印象に残るのが、#2:Is It Any Wonder?であるが、当時、ボーカルのトムはこの曲を"Rock'n Roll Beast(ロックンロールの野獣)"と表現していた。
野獣と呼ぶには些か野蛮さにかけると思ったが、激しくエフェクトをかけた独特のキーボードの音などは、1stアルバムのイメージを覆すには十分であり、この作品の持つ、陰鬱さを交えたおとぎ話のような世界観においては、うってつけの野獣であった。
アルバムの世界観は#1:Atlanticにより作られ、最後を締めくくる#12:The Flog Princeまで、一貫している(日本盤には#13:Let It Slideの収録がある)。
ジャケット画像の印象も相まって、アルバムを通して聴くことに、まるで一つの絵本を読んでいるかのような心地良さがある。
歌詞の内容こそKeaneらしいが、全編通じて非常に良く統一された、質の高いコンセプトアルバムである。
詳細については別の機会にしたいが、この、不思議な世界観を持ったアルバムを、個人的にはとても気に入っている。
2012/11/04
どんよりと曇った微妙な空模様:Sun/Two Door Cinema Club
Two Door Cinema ClubのアルバムBeaconより、#4:Sunが2ndシングルとしてリリースされたようで、PVが公開されている。
Sun/Two Door Cinema Club
PVは、公式サイトのトップページでも観ることができる。
http://twodoorcinemaclub.com/
トップページ上に大きく表示されるPV、以前はSleep Aloneだったが、シングルリリースに合わせてSunに替えられた模様。
この曲は、Beaconの中では一番好きで聴いていた曲である。
PVにはWhat You knowのように、健康的な女の子(そして彼女らの踊る、不可思議なダンス!)が登場している。
撮影場所は北西フランスのル・アーブル(Le Havre)という町だそう。
明るさがありながらもどんよりと曇った微妙な空模様は、この曲にマッチしていると感じる。
妙にハイテンションな周囲の人々(彼らは映像の中で、風景のように表れては消えていく)と、それらとは対照的にぼんやりと物思いに耽っている様子であり、上の空なバンドのテンションとの温度差もまた、曲にマッチしている。
PVを観て、歌詞を読んで、この曲が切ない曲だということに気が付いた。
Sun/Two Door Cinema Club
PVは、公式サイトのトップページでも観ることができる。
http://twodoorcinemaclub.com/
トップページ上に大きく表示されるPV、以前はSleep Aloneだったが、シングルリリースに合わせてSunに替えられた模様。
この曲は、Beaconの中では一番好きで聴いていた曲である。
PVにはWhat You knowのように、健康的な女の子(そして彼女らの踊る、不可思議なダンス!)が登場している。
撮影場所は北西フランスのル・アーブル(Le Havre)という町だそう。
明るさがありながらもどんよりと曇った微妙な空模様は、この曲にマッチしていると感じる。
妙にハイテンションな周囲の人々(彼らは映像の中で、風景のように表れては消えていく)と、それらとは対照的にぼんやりと物思いに耽っている様子であり、上の空なバンドのテンションとの温度差もまた、曲にマッチしている。
PVを観て、歌詞を読んで、この曲が切ない曲だということに気が付いた。
2012/10/31
寒い冬に適した音楽:X&Y/Coldplay
曲には、それぞれの相性の良いシチュエーションというものがある。
ドライブに適した音楽、クラブで踊るのに適した音楽、穏やかな日曜日の午後に適した音楽。
音楽の愛好者は、様々な音楽を、自らの好むシチュエーションに合わせて楽しむ。そして利用する、消費する。
季節というのは、そういったシチュエーションの中の、大切な一つである。
急速に冷え込む今のような季節には、冬に聴く音楽のことを思わずにはいられない。
個人的な見解ではあるが、ColdplayのX&Yは、冬に聴くのにうってつけの音楽だ。
このアルバムには寒い冬、それも窓を開けて空気を吸い込むと身体中の血管が縮こまるような、とびきり寒い冬が合う。
なぜそれがColdplayのX&Yなのか。
例えばEric ClaptonのReptileではダメなのか。
人を説得できるような理屈で説明しろと言われても難しいが、とにかくそう感じるのだから仕方がない。
(でも、寒い冬にThe Beach BoysのPet Soundsを聴きたいという好き者はあまりいないだろう。もしいたとしたら、その人は音楽と相当律儀に付き合っているか、古き良き時代の思い出に浸って現実逃避をしているかのどちらかに違いない)
"cold"という単語から短絡的な連想をしているだけであるのか、或いはジャケットの濃いブルーが自分にそう感じさせるのかは分からないが、自分にとって、ColdplayのX&Yは冬に聴くアルバムなのである。
X&Yは、2005年にリリースされたColdplayの3rdアルバムである。
冒頭の1曲:Square Oneは、”ツァラトゥストラはかく語りき ”を思わせる重厚な出だしから始まり、神秘的なシンセサイザーのサウンドは宇宙のように暗くて広く冷たい空間を思わせ、このイメージがアルバムの印象を決定づけている。
1stアルバム(Parachutes)、2ndアルバム(A Rush Of Blood To The Head 邦題:静寂の世界)からのファンの間では、3rdアルバムでColdpleyはロックバンドらしさを失ったと言われており、前作までの作品と比べて装飾性の高くなった本作の評価は割れているようだが、自分は4th:Viva La Vida Or Death And All His Friends(邦題:美しき生命)、5th:Mylo Xylotoを含めても、本作が一番好きである。
バンド感のある曲(The Hardest Part)やシンセの音が美しい曲(White Shadows)など曲ごとに個性はあるが、アルバムとして非常に綺麗にまとまっている。
Brian Enoと手を組んだ次作は本作の方向性を更に強めたものとなっているが、いくらか前衛的すぎる嫌いがあり、アルバムとしての完成度は本作の方が上回っている。
個人的には、先行シングルであるSpeed Of Soundではなく、それ以外の曲が気に入っている。
本作はまた、良質なヘッドフォンでじっくりと聴きたい作品である。
Wikipedia
http://www.coldplay.com/
ドライブに適した音楽、クラブで踊るのに適した音楽、穏やかな日曜日の午後に適した音楽。
音楽の愛好者は、様々な音楽を、自らの好むシチュエーションに合わせて楽しむ。そして利用する、消費する。
季節というのは、そういったシチュエーションの中の、大切な一つである。
急速に冷え込む今のような季節には、冬に聴く音楽のことを思わずにはいられない。
個人的な見解ではあるが、ColdplayのX&Yは、冬に聴くのにうってつけの音楽だ。
このアルバムには寒い冬、それも窓を開けて空気を吸い込むと身体中の血管が縮こまるような、とびきり寒い冬が合う。
なぜそれがColdplayのX&Yなのか。
例えばEric ClaptonのReptileではダメなのか。
人を説得できるような理屈で説明しろと言われても難しいが、とにかくそう感じるのだから仕方がない。
(でも、寒い冬にThe Beach BoysのPet Soundsを聴きたいという好き者はあまりいないだろう。もしいたとしたら、その人は音楽と相当律儀に付き合っているか、古き良き時代の思い出に浸って現実逃避をしているかのどちらかに違いない)
"cold"という単語から短絡的な連想をしているだけであるのか、或いはジャケットの濃いブルーが自分にそう感じさせるのかは分からないが、自分にとって、ColdplayのX&Yは冬に聴くアルバムなのである。
X&Yは、2005年にリリースされたColdplayの3rdアルバムである。
冒頭の1曲:Square Oneは、”ツァラトゥストラはかく語りき ”を思わせる重厚な出だしから始まり、神秘的なシンセサイザーのサウンドは宇宙のように暗くて広く冷たい空間を思わせ、このイメージがアルバムの印象を決定づけている。
1stアルバム(Parachutes)、2ndアルバム(A Rush Of Blood To The Head 邦題:静寂の世界)からのファンの間では、3rdアルバムでColdpleyはロックバンドらしさを失ったと言われており、前作までの作品と比べて装飾性の高くなった本作の評価は割れているようだが、自分は4th:Viva La Vida Or Death And All His Friends(邦題:美しき生命)、5th:Mylo Xylotoを含めても、本作が一番好きである。
バンド感のある曲(The Hardest Part)やシンセの音が美しい曲(White Shadows)など曲ごとに個性はあるが、アルバムとして非常に綺麗にまとまっている。
Brian Enoと手を組んだ次作は本作の方向性を更に強めたものとなっているが、いくらか前衛的すぎる嫌いがあり、アルバムとしての完成度は本作の方が上回っている。
個人的には、先行シングルであるSpeed Of Soundではなく、それ以外の曲が気に入っている。
本作はまた、良質なヘッドフォンでじっくりと聴きたい作品である。
Wikipedia
http://www.coldplay.com/
2012/10/28
ブリティッシュロックへの回帰:Don't Believe The Truth/Oasis
個人的には、彼らの6枚目のアルバムであるDon't Believe The Truthが気に入っている。
3rdアルバム以降、アルバムの評価的に決して成功しているとはいえなかったOasisであるが、本作では王道のブリティッシュロックに回帰し、それが見事に成功している。
1stアルバム、2ndアルバムの成功、歯に衣着せぬ物言いや、しばしばメディアを騒がす荒っぽいエピソード、兄弟喧嘩…と、注目度は圧倒的に高く、名実ともに英国を代表するバンドであったことは周知のところではあるが、本作品によってその地位は確固としたものとなったように思う。
何と言っても好きなのは、アルバムの1曲目であるTurn Up The Sunだ。
カウントアップから始まるイントロ、控えめにリズムを刻む鈴の音、アナログなギターの音。
音からは、枯れた荒野や沈みゆく夕日といったイメージが連想される。
曲から滲み出るハードボイルドな雰囲気が、たまらなく格好いい。
Turn Up The Sun/Oasis
イントロの格好良さ、そしてストイックかつドライなイメージが印象的な曲である。
こんな曲から始まるアルバムが、名作でないわけがない。
そして、本アルバムの1stシングルにして、後期に発表された曲の中では圧倒的な支持を得ているこの曲。
Lyla/Oasis
Turn Up The Sunと同じく、冒頭のギターから、ただただ格好いい曲である。
他にも、The Importance Of Being IdleやLet There Be Loveのように、ノエルのボーカルで優れた曲もある。
全体的にギターの使い方が土臭くて、それがとても良い。
また、前作までとの違いとして、ボーカルの音に重みが増しているように感じられる。
6枚目というタイミングで、何の脈絡もなくこれほど存在感のある作品を残すことができたのは、バンドにとって重要なことであったに違いない。
スタジアムのような巨大な会場で、大人数を前にして演奏するのに耐えうるだけのキャパシティーを持ったバンドというのは、そうそう数が多いものではないと思うが、本作によって、Oasisはそういった高みに到達した感がある。
本作がなければ、Oasisというバンドの痕跡は今ほど強く残っていなかっただろう。
純粋にそう思えるほどの作品である。
本作がリリースされた当時の熱狂を垣間見ることのできる映像を発見した。
Live Manchester 2005/Oasis
ちなみに2005年は音楽的に豊作の年であり、他のバンドからもいくつか優れたアルバムが発表されているのだが、その話はまた別の機会にということで。
イントロの格好良さ、そしてストイックかつドライなイメージが印象的な曲である。
こんな曲から始まるアルバムが、名作でないわけがない。
そして、本アルバムの1stシングルにして、後期に発表された曲の中では圧倒的な支持を得ているこの曲。
Lyla/Oasis
Turn Up The Sunと同じく、冒頭のギターから、ただただ格好いい曲である。
他にも、The Importance Of Being IdleやLet There Be Loveのように、ノエルのボーカルで優れた曲もある。
全体的にギターの使い方が土臭くて、それがとても良い。
また、前作までとの違いとして、ボーカルの音に重みが増しているように感じられる。
6枚目というタイミングで、何の脈絡もなくこれほど存在感のある作品を残すことができたのは、バンドにとって重要なことであったに違いない。
スタジアムのような巨大な会場で、大人数を前にして演奏するのに耐えうるだけのキャパシティーを持ったバンドというのは、そうそう数が多いものではないと思うが、本作によって、Oasisはそういった高みに到達した感がある。
本作がなければ、Oasisというバンドの痕跡は今ほど強く残っていなかっただろう。
純粋にそう思えるほどの作品である。
本作がリリースされた当時の熱狂を垣間見ることのできる映像を発見した。
Live Manchester 2005/Oasis
ちなみに2005年は音楽的に豊作の年であり、他のバンドからもいくつか優れたアルバムが発表されているのだが、その話はまた別の機会にということで。
2012/10/16
どうにも放っておけない音楽/The Royal Concept
http://www.royalconceptband.com/
スウェーデンのストックホルム出身のバンド、The Royal Concept。
御世辞にもあまり格好いいとはいえないバンド名であるが、どうにも放っておけない音楽を鳴らしている。
Gimme Twice/The Royal Concept
PVはこちら:http://www.youtube.com/watch?v=Bp-S31NZ4-Y
EPを聴いてまず思ったのは”Phoenixに似ている”ということであるが、同じことを感じた人は多いようで、iTunesのレビューや他のブログでもPhoenixに似ているということが仕切りに言われている。
#1 Gimme Twice、#4 D-D-Danceは特にPhoenixを彷彿とさせるし(#1はアルバム「Wolfgang Amadeus Phoenix」に収録されたGirlfriendという曲を連想させる)、#2 Goldrushed、#3 Knocked UpなんかはThe Strokesっぽくもあったりする(ボーカルの声にかけたエフェクトと電子的な音から、特にアルバム「Angles」のテイストに近いものを感じる)。
D-D-Dance/The Royal Concept
PVはこちら:http://www.youtube.com/watch?v=MkYgQBuXhes
この曲は、PhoenixのLisztmaniaという曲(アルバム:Wolfgang Amadeus Phoenixに収録)に非常に近い雰囲気を持っている。
上記動画ではバンド名がThe Conceptとなっているが、こちらは元々のバンド名で、たまたま同名のバンドがいたことから途中でThe Royal Conceptへと改称したとのこと。
2012年7月24日にリリースされた「The Royal Concept EP」が事実上のデビュー盤であったり、Wikipediaにもまだバンドの記事がなかったりと、まさにデビューしたてのバンドであるが、このEPは非常に面白い。
関連記事:バンドの秘めたポテンシャル/The Royal Concept
http://altblg.blogspot.jp/2013/05/the-royal-concept.html
スウェーデンのストックホルム出身のバンド、The Royal Concept。
御世辞にもあまり格好いいとはいえないバンド名であるが、どうにも放っておけない音楽を鳴らしている。
Gimme Twice/The Royal Concept
PVはこちら:http://www.youtube.com/watch?v=Bp-S31NZ4-Y
EPを聴いてまず思ったのは”Phoenixに似ている”ということであるが、同じことを感じた人は多いようで、iTunesのレビューや他のブログでもPhoenixに似ているということが仕切りに言われている。
#1 Gimme Twice、#4 D-D-Danceは特にPhoenixを彷彿とさせるし(#1はアルバム「Wolfgang Amadeus Phoenix」に収録されたGirlfriendという曲を連想させる)、#2 Goldrushed、#3 Knocked UpなんかはThe Strokesっぽくもあったりする(ボーカルの声にかけたエフェクトと電子的な音から、特にアルバム「Angles」のテイストに近いものを感じる)。
D-D-Dance/The Royal Concept
PVはこちら:http://www.youtube.com/watch?v=MkYgQBuXhes
この曲は、PhoenixのLisztmaniaという曲(アルバム:Wolfgang Amadeus Phoenixに収録)に非常に近い雰囲気を持っている。
上記動画ではバンド名がThe Conceptとなっているが、こちらは元々のバンド名で、たまたま同名のバンドがいたことから途中でThe Royal Conceptへと改称したとのこと。
2012年7月24日にリリースされた「The Royal Concept EP」が事実上のデビュー盤であったり、Wikipediaにもまだバンドの記事がなかったりと、まさにデビューしたてのバンドであるが、このEPは非常に面白い。
Product Description
2012 release from the Swedish quartet. Over the past year, The Royal Concept managed to catch the attention of the blog-o-sphere and play to rabid live audiences. 'D-D-Dance' reached #2 on Hype Machine, while 'Gimme Twice' hit #3. They began to pack houses in Sweden, selling out shows of their own. Lava Records founder and CEO Jason Flom was transfixed by the band's presence and sound from the second he first saw them, signing them earlier this year. ''You can't really put it into words,'' he affirms. ''There's an intangible magic to this band. A&R usually isn't this easy!''(Amazon.co.jpより)
関連記事:バンドの秘めたポテンシャル/The Royal Concept
http://altblg.blogspot.jp/2013/05/the-royal-concept.html
2012/10/10
ティーンエイジャーのどこか頼りなげな感じ/Smith Westerns
Smith Westerns、なんとも微妙な空気感を持つバンドである。
Weekend/Smith Westerns
彼らの2ndアルバムであるDye It Blondeの1曲目、Weekendは良い。曲も良いし、PVも良い。
PVの中の彼らは、空虚でナンセンスな日常を過ごしているように見える。何をするでもなく、ただ時間が経過するのを待っているだけのように感じられるのだ。
蛍光イエローのチーズの色も、不自然にグリーンなソーダの色も、どちらも極めて非日常的だが、彼らにとってはそれはごく当たり前の日常なのである。
アルバム全体を通して聴いてみると、その完成度は決して高いとは言えない。だからこそ、その時限りの空気みたいなものが表現されているような気がして、多少の荒削りさが、逆に作品の質を高めているようにすら感じる。
これらの曲を作ったのは、シカゴに住む若干二十歳の3人組なのだ。そう思って聴いていると、いろいろと感じるものはある。
ティーンエイジャーのどこか頼りなげな感じや、自分を振り回す感情の起伏なんてどこ吹く風といった風情で飄々としている様が、何とも切ない。そんなアルバムである。
Imagine Pt.3/Smith Westerns
彼らの原点にはブリットポップがあるそうで、アルバムは全体を通してノスタルジックな雰囲気を醸している。
アルバム5曲目"Fallen In Love"、7曲目"Only One"は、特にブリットポップらしい雰囲気を持っている。
(冒頭のバンドHPにて、アルバムDye It Blondeの全曲が試聴可能)
どの曲もメロディは良質であり、まだ歳もそこそこの彼らが、勢いに頼ることをせず、雰囲気でここまで聴かせるアルバムを作ったことは素直に素晴らしいと思う。
Smith Westernsは、イリノイ州シカゴ出身のインディーロックバンドである。彼らの音楽はDavid Bowie、T.Rex、そしてBrit Popからの影響を受けている。バンド自身の名前を冠したデビューアルバムは、HoZac Recordsより2009年6月5日にリリースされた。アルバムのほとんどは、冬から初春にかけてのMax Kakasek's basementで録音された。彼らは2011年1月18日に発売リリースされた最新アルバムであるDye It Blondeより、ニューシングル"Weekend"を2010年11月4日にリリースした。最近では、彼らはArctic MonkeysのSuck It And Seeツアーにて前座を務めている。
Smith Westerns are an indie rock band from Chicago, Illinois. Their musical influences include David Bowie, Marc Bolan, T. Rex and Brit Pop.Their self-titled debut album was released on HoZac Records on June 5, 2009. Most of the album was recorded throughout the winter and early spring in Max Kakacek's basement.They released a new single, "Weekend", on November 4, 2010, from their most recent album Dye It Blonde, which was released on January 18, 2011.Most recently, they have been opening band for the Arctic Monkeys in their Suck It and See Tour.(Wikipediaより抜粋)
2012/10/05
よっぽど青く、衝動的であり/The Vaccines
http://www.thevaccines.co.uk/gb/splash/
2011年に1st、そして2012年に2ndとハイペースでのアルバムリリースとなった。
http://www.youtube.com/watch?v=bFUKrsDDChE
音楽性としては主流も主流、ど真ん中のロックを鳴らしているといった印象。2ndアルバムでありながら1stよりもよっぽど青く、衝動的であり、聴いていてわくわくするものがある。若干の物憂げさと暗い広がりみたいなものを感じさせた1stと違い、地に足のついている感がある。
前作にも増して土臭さの残るアルバムであり、キャッチーなポップアルバムのようにすぐには馴染んでこない。ボディーブローのように、じわじわと効いてくるアルバムであると思う。No Hope、Teenage Iconといった単体で非常に強い力を持った曲の存在により、他の曲の存在感が薄れてしまっているが、アルバム全体を通して正統的なガレージロックが貫かれている。正直こういったアルバムがチャートで1位を取るというのは、ちょっとした驚きである。
コントラストはArctic Monkeysと比べて若干ぼやけており、破天荒さではThe Libertinesに及ばない。そういった点で多少の退屈さはあるものの、バンドとして表現している音楽性の完成度は高い。上記の2曲や、1stに収録されたWreckin' Bar (Ra Ra Ra)やIf You Wannaのような優れた曲の存在もあり、個人的にはバンドの今後の行方からは、目が離せない。
2011年に1st、そして2012年に2ndとハイペースでのアルバムリリースとなった。
数多のバンドが1stで燦然としたデビューを飾り、2ndアルバム以降その輝きを失っていくところを見てきたが、彼らはどうなるであろうか。
Teenage Icon/The Vaccines(リンク先はPV)
音楽性としては主流も主流、ど真ん中のロックを鳴らしているといった印象。2ndアルバムでありながら1stよりもよっぽど青く、衝動的であり、聴いていてわくわくするものがある。若干の物憂げさと暗い広がりみたいなものを感じさせた1stと違い、地に足のついている感がある。
前作にも増して土臭さの残るアルバムであり、キャッチーなポップアルバムのようにすぐには馴染んでこない。ボディーブローのように、じわじわと効いてくるアルバムであると思う。No Hope、Teenage Iconといった単体で非常に強い力を持った曲の存在により、他の曲の存在感が薄れてしまっているが、アルバム全体を通して正統的なガレージロックが貫かれている。正直こういったアルバムがチャートで1位を取るというのは、ちょっとした驚きである。
コントラストはArctic Monkeysと比べて若干ぼやけており、破天荒さではThe Libertinesに及ばない。そういった点で多少の退屈さはあるものの、バンドとして表現している音楽性の完成度は高い。上記の2曲や、1stに収録されたWreckin' Bar (Ra Ra Ra)やIf You Wannaのような優れた曲の存在もあり、個人的にはバンドの今後の行方からは、目が離せない。
イギリスではリリースされた週のアルバムチャートで1位を記録している。2位はTwo Door Cinema Club。1995年のoasisとblurではないが、同じような境遇にある2つのバンドがチャートの1、2位を占めるということで、何だか熱くなるものがある。どちらもインディーロックバンドであり、ともに2ndアルバム。
The Vaccinesは、一つの時代を創り上げたOasisやThe Strokes、同じ英国のロックバンドであるThe LibertinesやKasabian、Arctic Monkeysなどと同列に語られるようなバンドとなるだろうか。
The Vaccinesは、一つの時代を創り上げたOasisやThe Strokes、同じ英国のロックバンドであるThe LibertinesやKasabian、Arctic Monkeysなどと同列に語られるようなバンドとなるだろうか。
デビュー時のインパクトをバンドとしての個性に昇華させ、更に次の次元へと進めるバンドと、そうでないバンドとの違いについて考えてみると、思い浮かぶのはその熱量を如何に維持することができるかである。
デビュー時に音楽シーンへ投じた熱量を、どういった層にどの程度浸透させられるか、その深さと広さによって、バンドの立ち位置は決まる。
余談であるが、バンドのデビューというものは、株式の上場に相似している。少々強引に喩えると、インディーズバンドを未上場企業、メジャーデビューを株式上場とみることもできる。大物バンドは巨大企業に、音楽性やジャンルの違いは業種の違いに、色々と喩えて考えてみるのも面白い。
デビュー時に音楽シーンへ投じた熱量を、どういった層にどの程度浸透させられるか、その深さと広さによって、バンドの立ち位置は決まる。
余談であるが、バンドのデビューというものは、株式の上場に相似している。少々強引に喩えると、インディーズバンドを未上場企業、メジャーデビューを株式上場とみることもできる。大物バンドは巨大企業に、音楽性やジャンルの違いは業種の違いに、色々と喩えて考えてみるのも面白い。
The Vaccinesは、イギリスのインディロックバンド。2010年にウェストロンドンで結成された。バンドのデビューアルバムであるWhat Did You Expect from the Vaccines?(コロンビアレコードより2011年3月14日にリリース)は、イギリスのアルバムチャートで4位にランクインした。彼らはRamonesやThe Strokes、Jesus And Mary Chainといったバンドと比較される。しかし、バンド自身は50年代のrock 'n' rollから80年代のAmerican hardcore、そして良質なポップミュージックからの影響を公言している。彼らは広い範囲をツアーで周り、The Walkman、The Stone Roses、Arctic Monkeys、そしてArcade Fireと同様のバンドとして認識されている。
The Vaccines are an English indie rock band who formed in West London in 2010. The band's debut album, What Did You Expect from the Vaccines?, was released through Columbia Records on 14 March 2011 and reached number 4 in the UK Album Chart . They drew comparisons to Ramones, The Strokes and The Jesus And Mary Chain. The band, however, talked of influences ranging from "'50s rock 'n' roll to 80s American hardcore and good pop music". They've toured extensively and have opened for the likes of The Walkmen, The Stone Roses, Arctic Monkeys and Arcade Fire. (Wikipediaより抜粋)
2012/09/30
捕らわれた感じのしない、飄々とした/Two Door Cinema Club
バンドの色はポップ×ロック×ダンスといった具合であり、いうならば”ロックをベースにポップを鳴らし、ダンスのテイストを混ぜた”といった感じである。2007年に北アイルランドで結成され、所属はフランスのレコードレーベルKitsune。
いわゆるBritish Rockといった感じでは全然ないが(British Rockといえば、Two Door Cinema Clubと同時期に2ndアルバムをリリースし、チャートを賑わしたThe Vaccinesはその正統なDNAを継いでいるように思う)、一過性のバンドのような軽さはなく、1stの時点で十分にバンドのオリジナリティは確立されているように思う。
特筆すべきなのは、メロディのセンスがずば抜けて良いことである。
1st、2nd、どちらのアルバムも全ての曲が,聴ける。踊れる。
キャッチーな曲もあり、綺麗なメロディの曲もある。
ルックスやPV、曲からの印象として、alternativeな雰囲気を持っているところも魅力的である。
アルバムを何度も繰り返し聴き、久しぶりに、長い時間をかけて付き合って行きたいと思えるバンドと出会えたと感じている。
Beacon(Album Trailer)
Undercover Martyn/Two Door Cinema Club
I Can Talk/Two Door Cinema Club
様々なレビューを見ていると”1stの荒削りな感じが好き”といった声や”2ndになって洗練された雰囲気が出てしまったのが残念”といった声が散見されるけれど、自分も現時点では1stの方が好きである。上のPVはどちらも1stアルバムに収録された曲だが、デビューしたての青さみたいなものがあって、自由な空気が流れているところが何とも爽快でいい。
そう考えてみると、音楽性の個性に加えて、何かに捕らわれた感じのしない、飄々としたところが彼らの魅力であるなと思う(1stや2ndアルバムというと、勢いや熱量で振り切ろうとするバンドが少なくないが、彼らは飽くまでも飄々としているのだ)。
1stアルバムは英国でプラチナディスクとなっているが、多くのバンドにとって鬼門である2ndアルバムも英国ヒットチャートで上位につけており、大いに成功していると言える。
今後が非常に楽しみなバンドである。
2012/09/25
アルバムレビュー:ランドマーク(B面)/ASIAN KUNG-FU GENERATION
ランドマーク、ファーストインプレッションの後半。
B面
B面
7.それでは、また明日
初めは平坦なベースがシンプル過ぎると感じていたけれど、HMVで視聴し、”これぞアジカン”的な正統派ロックにコロッときてしまった曲。レコード屋の試聴機は低音が豊かなので、こういう直球ストレートな曲を聴いてしまうと一発KOである(新曲が発売された後の楽しみの一つは、レコード屋に行き大きめのボリュームで試聴することである。レコード屋の試聴機というのはよく出来ているもので、ヘッドホンの音作りがいい塩梅になっているため、気になった曲を大きめのボリュームで試聴すると大抵ガツンとやられてしまう)。
同系列にあるアジカン的な正統派ロックな曲を挙げてみると、「遥か彼方」や「フラッシュバック」、「未来の破片」、「リライト」、「ワールドアパート」、「アフターダーク」などが思い浮かぶ。こうやって並べてみると、やはりこういった曲は初期の頃に偏っている。
これらの曲の共通点は、テンポが早く激しい曲であるということもあるが、この曲はその中にあって比較的、ストイックな曲である(上記の曲の中では特に、遥か彼方、未来の破片、ワールドアパートに近い)。最近のアジカンには珍しく、ポップな雰囲気よりもロックな雰囲気が勝る(パワーポップとロックの中間くらいか)。最後のサビの手前、曲のテイストが変わる間奏部分もアジカンらしくていい。
初期のファンにとってみれば、数年ぶり、待望のキラーチューンであると思う。
B面の一曲目がこの曲から始まるということは、初期のアルバムを彷彿とさせる(崩壊アンプリファー、君繋ファイブエム、ソルファはみな、アッパーな曲から始まるアルバムである)。
個人的には、PVの回る後藤氏が好き。
8.1980
重厚感がありながらそれほど効きづらくない。適度にポップであり、バランスがすごく良い曲。アルバムの中では多分それほど目立つことのない一曲であると思われるが、秀逸な一曲であると思う。
この優れたバランス感覚が、バンドの成長を感じさせる。
「それでは、また明日」に続いて、山田氏が作曲に名を連ねる一曲(優れたソングライターである)。
9.マシンガンと形容詞
タイトルが印象的な曲。
曲の構成といい、雰囲気といい、「世紀末のラブソング」の亜種といえる曲である(歌詞には世紀末という単語が出てくる)。
透き通った感じの電子音から受ける印象は、「世紀末のラブソング」のように暗いものではないため、アルバムのバランスを損なっていない。
10.レールロード
曲のタイトルや雰囲気によるものであろうか、レールを走る列車のイメージが脳裏を掠める。サビ手前のメロディが好きである。
エンディングのような雰囲気を持つ曲でもある。
11.踵で愛を打ち鳴らせ
前曲であるレールロードのエンディング感を受け止めた上で、そこでアルバムが終わりだと感じさせず、聴衆を更に高い位置へと引き上げるほどのスケール感を持った曲。
穏やかなイントロからファンファーレのように明るいメロディを経て、サビまで段々と登っていく。曲の構成やスケール感などは「ブラックアウト」を思わせる。
全体のまとまりの良さやメロディラインは素晴らしく、アルバム中最高の完成度を誇る曲だと思う。
アルバムの華やかなエンディングを飾る一曲。
12.アネモネの咲く春に
アナログなギターの音が他の曲とは違った曲。
アルバムの曲をひと通り終えて、アンコールに弾き語りのような気楽さで一曲歌った、といった風情を感じる(実際、この曲はライブでは弾き語りで歌われるらしい)。
思いをストレートに表現しない歌詞は何とも絶妙。
個人的には、震災の発生により様々な思惑が混沌と犇めき合うようになった今の状況において、緩やかな”善意”みたいなものが損なわれていることを憂いているように感じた。
全体を通して聴いてみると、本作はやはり、優れたポップアルバムである。
各曲の持つ熱量にバラつきが少なく、日常生活において、気軽に手に取って聴くことのできるアルバムであるといえる(これまでのアルバムも好きだが、個性の強いヘビーな曲と比較的ライトな曲が混在しているアルバムを聴くことは、結構体力を消耗するし状況を選ぶ)。
新しいアルバムと出会った後は、まず飽きるほどの高い頻度で聴き続け、ふとしたタイミングで夢から覚めたようにそれらと距離を置き、しばらくしてから適度な距離感で接近し、その後つかず離れずの関係を保つというのが個人的なスタイルであるが、本作とはコンスタントな付き合いができそうな気がする(異性との付き合い方の話をしているみたいだ)。
曲の構成といい、雰囲気といい、「世紀末のラブソング」の亜種といえる曲である(歌詞には世紀末という単語が出てくる)。
透き通った感じの電子音から受ける印象は、「世紀末のラブソング」のように暗いものではないため、アルバムのバランスを損なっていない。
10.レールロード
曲のタイトルや雰囲気によるものであろうか、レールを走る列車のイメージが脳裏を掠める。サビ手前のメロディが好きである。
エンディングのような雰囲気を持つ曲でもある。
11.踵で愛を打ち鳴らせ
前曲であるレールロードのエンディング感を受け止めた上で、そこでアルバムが終わりだと感じさせず、聴衆を更に高い位置へと引き上げるほどのスケール感を持った曲。
穏やかなイントロからファンファーレのように明るいメロディを経て、サビまで段々と登っていく。曲の構成やスケール感などは「ブラックアウト」を思わせる。
全体のまとまりの良さやメロディラインは素晴らしく、アルバム中最高の完成度を誇る曲だと思う。
アルバムの華やかなエンディングを飾る一曲。
12.アネモネの咲く春に
アナログなギターの音が他の曲とは違った曲。
アルバムの曲をひと通り終えて、アンコールに弾き語りのような気楽さで一曲歌った、といった風情を感じる(実際、この曲はライブでは弾き語りで歌われるらしい)。
思いをストレートに表現しない歌詞は何とも絶妙。
個人的には、震災の発生により様々な思惑が混沌と犇めき合うようになった今の状況において、緩やかな”善意”みたいなものが損なわれていることを憂いているように感じた。
全体を通して聴いてみると、本作はやはり、優れたポップアルバムである。
各曲の持つ熱量にバラつきが少なく、日常生活において、気軽に手に取って聴くことのできるアルバムであるといえる(これまでのアルバムも好きだが、個性の強いヘビーな曲と比較的ライトな曲が混在しているアルバムを聴くことは、結構体力を消耗するし状況を選ぶ)。
新しいアルバムと出会った後は、まず飽きるほどの高い頻度で聴き続け、ふとしたタイミングで夢から覚めたようにそれらと距離を置き、しばらくしてから適度な距離感で接近し、その後つかず離れずの関係を保つというのが個人的なスタイルであるが、本作とはコンスタントな付き合いができそうな気がする(異性との付き合い方の話をしているみたいだ)。
2012/09/19
アルバムレビュー:ランドマーク(A面)/ASIAN KUNG-FU GENERATION
http://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/AKG/
ASIAN KUNG-FU GENERATIONの7枚目のアルバム、ランドマークがリリースされた。
ひと通り聴いてみてのファーストインプレッションについて。
アルバム全体を通して、優れたポップアルバムという印象を持った。
特筆すべき点は何より、聴き易いアルバムであるということである。
バンドがデビューしてまだ間もない頃の衝動的な曲でアジカンを好きになったファンは、近年、デビュー当時のような疾走感や荒っぽさのある曲が発表されないことを嘆いているが、残念ながらこのアルバムはそういった方向性を突き詰めたものではない。
変に色がついておらず聴き易い作品であり、そういった点において本作は、優れたポップアルバムであると言える。
どこかで「ミスチルのアルバムのようだ」と書かれているのを見て、ファンとしては「そんなことはないだろう」と思ってしまったのだが、ポップで聴き易いという点を考えると、あながち的外れな指摘ではないとも思う(もちろん曲調は違うが、敷居の低さという点において)。
本作にはCD音源とは違ったリマスタリングによるアナログ盤があり、A面6曲、B面6曲で構成されている。
自分はCDで聴いているが、このA面、B面というのはなるほどよく考えられており、本作は前半の6曲と後半の6曲が、それぞれミニアルバムとして個々に聴けるくらいに綺麗にまとまっている。
なので、このアルバムについては、A面、B面として捉えるのが的確であろうと思う。
アルバムリリースから1週間。ファーストインプレッションについて。
A面
1.All right part2
入り口である1曲目にこの曲を配置したことは、アルバムへの導入をスムーズにするという点において成功している。
この曲は2011年のNANO-MUGEN FES.用にリリースされたコンピレーションに収録されており、収録曲の中でも比較的古い曲である。それ故、真新しさはないが、磐石な選曲であるといえる。
アルバムの印象は一曲目に大分左右されると思うが、この曲の取っ付き易さによって、ランドマークの敷居はグッと低くなっている(収録曲の中では一番キャッチーな曲だと思う。実際、この曲がランドマークを聴くきっかけとなっている)。
バンド自身が度々語っているところによると、本作には、これまでのアルバムのように何らかのコンセプトが意図されていないそうだ。バンドにとっても聴衆にとっても、このアルバムに対しては肩肘を張る必要がなく、変に身構える必要もないということである。
収録にあたってASIAN KUNG-FU GENERATIONのみでの再録がなされるものと思っていたが、収録された曲にはNANO-MUGEN COMPILATION 2011と同じく、チャットモンチーのボーカル橋本絵莉子女史(えっちゃん)が参加している。
なお、表記はされていないが、アルバムヴァージョンのようである。
2.N2
2011年11月にリリースされたシングル「マーチングバンド」に収録されたカップリング曲。マーチングバンドが収録曲から外れている(ベスト盤には収録されている)のに対して、カップリングのこの曲が収録されるというのは意外であった。
シングルのマーチングバンドを聴いていないため、ちゃんと聴くのはこのアルバムが初めてであるが、”変わった曲”という第一印象とは違い、アルバムの一曲としては良い存在感を放っている。ボーカルやギターにかかった強いエフェクトが、曲全体の雰囲気をソリッドなものにしている。
N2はNo Nukesを意味していると言われている。
音楽がその歌詞によって様々な矛盾やフラストレーション、或いは何かしらの思いを表現することに何ら異存はないが、それらの内容に対して自分は冷静なスタンスをとっており、自身の生活とは一定の距離を置いたものとして捉えている。
この曲をアルバムに収録したことは、バンド(主にボーカル後藤氏)の明確な意思表示の現れであろう。こういった社会的な主張を含んだ曲は、ワールドワールドワールドにおけるNo.9などの前例があるが、不可思議で不可避な体制(戦争や資本主義社会といったもの)に抗い、鼓舞するロックやパンクというものを、音楽性ではなく”表現者のスタンス”や”曲に込めたメッセージ”として表現しようとする後藤氏の姿勢が感じられる。
3.1.2.3.4.5.6. Baby
歌詞がシンプルな曲。
出だしは明るい。テンポは良いが軽くなく、一つ一つの音はしっかりとしている。既存曲でる1、2曲目の前置きを終え、ようやくアルバムが始まったという印象を受ける(曲順では、1曲目の新曲がこの曲である)。
”愛を”という、歌詞カードに書けばたった2文字の言葉を、サビとして高らかに歌いあげるのは気持ちがいい。”愛を”は”I want”とも聴き取れる。
歌詞カードを見て”変わった曲”というイメージを持っていたが、一聴してすぐに好きになった。アルバム中、最も気に入った曲である。シンプルな歌詞を繰り返す分かりやすさと、クリアでキャッチーなメロディがとても良い。
最後のサビの前、曲のテンポが下がり喜多氏が高い声で歌う部分のギターの音は「夕暮れの紅(リライトc/w)」を彷彿とさせる。
4.AとZ
儀式的なドラムが印象的な曲。広い空間を感じさせるサビは、アジカンの新境地。自分はColdplayを連想した。
タイトルから感じられるとおり、歌詞はアルファベットを多様した言葉遊びであり、メッセージ性に富んだ曲でもある。こういった歌詞を、狙った感じを微塵も出さずに自然と曲に乗せてしまうところは、後藤氏の優れた才能であると思う。この曲に限らず、歌詞のセンスがとてもいい。
ちなみにTPPの後に出てくるCPZは、アダルトサイトを指しているといわれている。
5.大洋航路
タイトルから連想されるとおり、青い海や風の吹き抜ける港をイメージさせる明るさを持った、アップテンポの曲。サビのコーラスが気持ちいい。イメージといい音作りといい、サーフ ブンガク カマクラに通じる雰囲気を持った曲である。
6.バイシクルレース
PVが制作されていることから、アルバム中のハイライト曲であると思われる。
A面のラストを飾る曲であり、丁寧に作られた曲である。
静かに落ち着いた始まりから徐々にリズムを取り入れて行く演出は、淡々とした日常生活をイメージさせる(PVのように、何でもない、どこにでもありそうな街の風景が良く馴染む)。
”走る”や”自動車”ではなく、自転車をメタファーとして用いたのは秀逸であったと思う。
雰囲気は「ムスタング」に似ているが、イントロ・アウトロの電子音の澄んだ感触とサビの抑揚により、ムスタングのように暗さを感じる曲ではない。最後のサビの前、「漕ぎ出せ、走り出せ」の部分が好きである。
「遠く向こうから、雨の匂い」の部分では、ギターの音を聴いて「飛べない魚(ブルートレインc/w)」を思い出した。
B面に続く。
ランドマーク(B面)/ASIAN KUNG-FU GENERATION
ASIAN KUNG-FU GENERATIONの7枚目のアルバム、ランドマークがリリースされた。
アルバム全体を通して、優れたポップアルバムという印象を持った。
特筆すべき点は何より、聴き易いアルバムであるということである。
バンドがデビューしてまだ間もない頃の衝動的な曲でアジカンを好きになったファンは、近年、デビュー当時のような疾走感や荒っぽさのある曲が発表されないことを嘆いているが、残念ながらこのアルバムはそういった方向性を突き詰めたものではない。
変に色がついておらず聴き易い作品であり、そういった点において本作は、優れたポップアルバムであると言える。
どこかで「ミスチルのアルバムのようだ」と書かれているのを見て、ファンとしては「そんなことはないだろう」と思ってしまったのだが、ポップで聴き易いという点を考えると、あながち的外れな指摘ではないとも思う(もちろん曲調は違うが、敷居の低さという点において)。
本作にはCD音源とは違ったリマスタリングによるアナログ盤があり、A面6曲、B面6曲で構成されている。
自分はCDで聴いているが、このA面、B面というのはなるほどよく考えられており、本作は前半の6曲と後半の6曲が、それぞれミニアルバムとして個々に聴けるくらいに綺麗にまとまっている。
なので、このアルバムについては、A面、B面として捉えるのが的確であろうと思う。
アルバムリリースから1週間。ファーストインプレッションについて。
A面
1.All right part2
入り口である1曲目にこの曲を配置したことは、アルバムへの導入をスムーズにするという点において成功している。
この曲は2011年のNANO-MUGEN FES.用にリリースされたコンピレーションに収録されており、収録曲の中でも比較的古い曲である。それ故、真新しさはないが、磐石な選曲であるといえる。
アルバムの印象は一曲目に大分左右されると思うが、この曲の取っ付き易さによって、ランドマークの敷居はグッと低くなっている(収録曲の中では一番キャッチーな曲だと思う。実際、この曲がランドマークを聴くきっかけとなっている)。
バンド自身が度々語っているところによると、本作には、これまでのアルバムのように何らかのコンセプトが意図されていないそうだ。バンドにとっても聴衆にとっても、このアルバムに対しては肩肘を張る必要がなく、変に身構える必要もないということである。
収録にあたってASIAN KUNG-FU GENERATIONのみでの再録がなされるものと思っていたが、収録された曲にはNANO-MUGEN COMPILATION 2011と同じく、チャットモンチーのボーカル橋本絵莉子女史(えっちゃん)が参加している。
なお、表記はされていないが、アルバムヴァージョンのようである。
2.N2
2011年11月にリリースされたシングル「マーチングバンド」に収録されたカップリング曲。マーチングバンドが収録曲から外れている(ベスト盤には収録されている)のに対して、カップリングのこの曲が収録されるというのは意外であった。
シングルのマーチングバンドを聴いていないため、ちゃんと聴くのはこのアルバムが初めてであるが、”変わった曲”という第一印象とは違い、アルバムの一曲としては良い存在感を放っている。ボーカルやギターにかかった強いエフェクトが、曲全体の雰囲気をソリッドなものにしている。
N2はNo Nukesを意味していると言われている。
音楽がその歌詞によって様々な矛盾やフラストレーション、或いは何かしらの思いを表現することに何ら異存はないが、それらの内容に対して自分は冷静なスタンスをとっており、自身の生活とは一定の距離を置いたものとして捉えている。
この曲をアルバムに収録したことは、バンド(主にボーカル後藤氏)の明確な意思表示の現れであろう。こういった社会的な主張を含んだ曲は、ワールドワールドワールドにおけるNo.9などの前例があるが、不可思議で不可避な体制(戦争や資本主義社会といったもの)に抗い、鼓舞するロックやパンクというものを、音楽性ではなく”表現者のスタンス”や”曲に込めたメッセージ”として表現しようとする後藤氏の姿勢が感じられる。
3.1.2.3.4.5.6. Baby
歌詞がシンプルな曲。
出だしは明るい。テンポは良いが軽くなく、一つ一つの音はしっかりとしている。既存曲でる1、2曲目の前置きを終え、ようやくアルバムが始まったという印象を受ける(曲順では、1曲目の新曲がこの曲である)。
”愛を”という、歌詞カードに書けばたった2文字の言葉を、サビとして高らかに歌いあげるのは気持ちがいい。”愛を”は”I want”とも聴き取れる。
歌詞カードを見て”変わった曲”というイメージを持っていたが、一聴してすぐに好きになった。アルバム中、最も気に入った曲である。シンプルな歌詞を繰り返す分かりやすさと、クリアでキャッチーなメロディがとても良い。
最後のサビの前、曲のテンポが下がり喜多氏が高い声で歌う部分のギターの音は「夕暮れの紅(リライトc/w)」を彷彿とさせる。
4.AとZ
儀式的なドラムが印象的な曲。広い空間を感じさせるサビは、アジカンの新境地。自分はColdplayを連想した。
タイトルから感じられるとおり、歌詞はアルファベットを多様した言葉遊びであり、メッセージ性に富んだ曲でもある。こういった歌詞を、狙った感じを微塵も出さずに自然と曲に乗せてしまうところは、後藤氏の優れた才能であると思う。この曲に限らず、歌詞のセンスがとてもいい。
ちなみにTPPの後に出てくるCPZは、アダルトサイトを指しているといわれている。
5.大洋航路
タイトルから連想されるとおり、青い海や風の吹き抜ける港をイメージさせる明るさを持った、アップテンポの曲。サビのコーラスが気持ちいい。イメージといい音作りといい、サーフ ブンガク カマクラに通じる雰囲気を持った曲である。
6.バイシクルレース
PVが制作されていることから、アルバム中のハイライト曲であると思われる。
A面のラストを飾る曲であり、丁寧に作られた曲である。
静かに落ち着いた始まりから徐々にリズムを取り入れて行く演出は、淡々とした日常生活をイメージさせる(PVのように、何でもない、どこにでもありそうな街の風景が良く馴染む)。
”走る”や”自動車”ではなく、自転車をメタファーとして用いたのは秀逸であったと思う。
雰囲気は「ムスタング」に似ているが、イントロ・アウトロの電子音の澄んだ感触とサビの抑揚により、ムスタングのように暗さを感じる曲ではない。最後のサビの前、「漕ぎ出せ、走り出せ」の部分が好きである。
「遠く向こうから、雨の匂い」の部分では、ギターの音を聴いて「飛べない魚(ブルートレインc/w)」を思い出した。
B面に続く。
ランドマーク(B面)/ASIAN KUNG-FU GENERATION
2012/09/15
小気味の良い、素晴らしくポップな/Dogs Die In Hot Cars
http://www.dogsdieinhotcars.com/
ひねくれポップなアルバムの中にあっては比較的ストレートな曲であるが、それでも十分に個性的な曲である。
I Love You 'Cause I Have To/Dogs Die In Hot Cars
小気味の良い、素晴らしくポップな曲である。
バンドにとって唯一のオリジナルアルバム(唯一といっていいだろう。この、2004年に1stアルバムを発表したバンドは、ギタリストであるGary Smithの脱退により2ndアルバムの製作を断念し、事実上の解散状態となってしまった。バンドは2006年に一度活動を停止し、2008年より新たなアルバムの製作をスタートさせた。バンドは2ndアルバムのために書いた曲をネット上に公開し、リスナー有志によるリミックス作業を経てそれぞれの曲を完成させ、ダウンロード形式で2ndアルバムを発表している)において、この曲はまさにメインと呼ぶに相応しい曲だ。
バンドの独特なセンスと雰囲気、そしてXTCを彷彿とさせるボーカルが、この曲をひねくれポップの王道たらしめている。
2ndアルバムの趣向は、1stのそれとは異なったものとなっている。
それが数年を経たことによるバンドの音楽センスの変遷によるものなのか、ギタリストの脱退によるものなのか、はたまたリミックスによるものなのかは定かではないが、現在こういった曲を作っているバンドが、ひねくれポップという時代を経ているのは興味深い。
バンドのホームページにおける、非常に詳しいBiography ⇒ Past To Present
I Love You 'Cause I Have To/Dogs Die In Hot Cars
小気味の良い、素晴らしくポップな曲である。
バンドにとって唯一のオリジナルアルバム(唯一といっていいだろう。この、2004年に1stアルバムを発表したバンドは、ギタリストであるGary Smithの脱退により2ndアルバムの製作を断念し、事実上の解散状態となってしまった。バンドは2006年に一度活動を停止し、2008年より新たなアルバムの製作をスタートさせた。バンドは2ndアルバムのために書いた曲をネット上に公開し、リスナー有志によるリミックス作業を経てそれぞれの曲を完成させ、ダウンロード形式で2ndアルバムを発表している)において、この曲はまさにメインと呼ぶに相応しい曲だ。
バンドの独特なセンスと雰囲気、そしてXTCを彷彿とさせるボーカルが、この曲をひねくれポップの王道たらしめている。
2ndアルバムの趣向は、1stのそれとは異なったものとなっている。
それが数年を経たことによるバンドの音楽センスの変遷によるものなのか、ギタリストの脱退によるものなのか、はたまたリミックスによるものなのかは定かではないが、現在こういった曲を作っているバンドが、ひねくれポップという時代を経ているのは興味深い。
バンドのホームページにおける、非常に詳しいBiography ⇒ Past To Present
Dogs Die in Hot Cars is a Scottish band from St. Andrews consisting of members Craig Macintosh (vocals, guitar), Gary Smith (vocals, guitar) Ruth Quigley (vocals, keyboards, French horn), Lee Worrall (bass and glockenspiel) and Laurence Davey (drums and percussion). (Wikipediaより抜粋)
2012/09/14
二人の容姿を滑稽に見せる/The Last Shadow Puppets
http://thelastshadowpuppets.com
前回記事に掲載の What you know/Two Door Cinema Club にPVが似ているこの曲。
Two Door Cinema ClubのPVはカラフルだが、こちらは落ち着いたトーンの色調。
The Last Shadow Puppetsは、Arctic Monkeysが好きだったことがきっかけで関心を持ったのだが、このPVを観て虜になってしまった。
アナログなギターをポロロンと弾く歌い出しから、メランコリックなメロディが一気に盛り上がりを見せる曲。
物憂げでありながらも情熱的な曲調に合わせたシンプルな演出がアンバランスで、二人の容姿を滑稽に見せる。
当時、Alex Turnerは23歳、Miles Kaneは22歳。
この曲は、大学生時代に夜更かしをして試験勉強をしていた時にたまたま見つけたのだが、そのまま気に入って何度も繰り返し聴いていたのを覚えている。
前回記事に掲載の What you know/Two Door Cinema Club にPVが似ているこの曲。
Two Door Cinema ClubのPVはカラフルだが、こちらは落ち着いたトーンの色調。
The Last Shadow Puppetsは、Arctic Monkeysが好きだったことがきっかけで関心を持ったのだが、このPVを観て虜になってしまった。
アナログなギターをポロロンと弾く歌い出しから、メランコリックなメロディが一気に盛り上がりを見せる曲。
物憂げでありながらも情熱的な曲調に合わせたシンプルな演出がアンバランスで、二人の容姿を滑稽に見せる。
当時、Alex Turnerは23歳、Miles Kaneは22歳。
この曲は、大学生時代に夜更かしをして試験勉強をしていた時にたまたま見つけたのだが、そのまま気に入って何度も繰り返し聴いていたのを覚えている。
ラスト・シャドウ・パペッツ(The Last Shadow Puppets)は、イギリスのロックバンド。アークティック・モンキーズのアレックス・ターナーと、ラスカルズのマイルズ・ ケインによって結成された。その主旨は、デーモン・アルバーンによるゴリラズやジャック・ホワイトのラカンターズらと同様、サイド・プロジェクトとして興されたバンドである。
2012/09/12
意図も簡単にファンになってしまう/Two Door Cinema Club
http://twodoorcinemaclub.com/home
The Vaccinesの2ndアルバムが気になり、ネット上で記事を読んでいた際に見つけたバンド:Two Door Cinema Club
Sleep Alone/Two Door Cinema Club
この曲は、一聴してKeaneの3rdに近いテイストだと感じた。
ロックを基盤としており、バンドの曲であるが、ダンサブルな雰囲気。
少し高めに心地良く鳴らすギターの音が、とてもタイプである。
ニューヨーク辺りの、例えばThe Drumsなんかが鳴らす音とはぜんぜん違う。
これはイメージの問題かもしれないが、ニューヨークのバンドの鳴らす音はどこか無機的、ソリッドな感じがある。比較的ローコンテクスト。
それは軽快な曲(ex. Let's Go Surfing/The Drums)であっても変わらない。
乾いた空気の中に、とても軽い音楽が流れているイメージである。
安直ではあるが、カリフォルニアという単語が思い浮かぶ。よく晴れた青い空に乾いた空気。吹き抜ける風、乾いた夏。
イメージかもしれないが、これが欧州のバンドであると、軽快さの中にも何かしら有機的なものを感じる。
Two Door Cinema Clubからも然り。
もう一曲
What you know/Two Door Cinema Club
1stアルバムの8曲目である。
これは堪らない。
小刻みにテンポの良い音から始まるイントロの、耳障りは良いがどこかもの思わしげなギターを聴いただけで、意図も簡単にファンになってしまう。
トゥー・ドア・シネマ・クラブ(Two Door Cinema Club)は、2007年に北アイルランドのバンガー/ドナガディーで結成されたエレクトロ・ポップ/インディー・ロックバンド。
アレックス・トリンブル、ケヴ・ベアード、サム・ハリデーの3人からなるドラムレスの3ピース・バンド(Wikipediaより抜粋)
登録:
コメント (Atom)